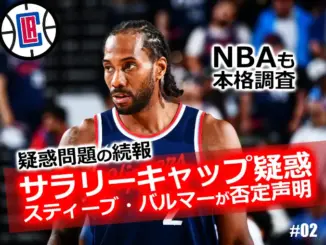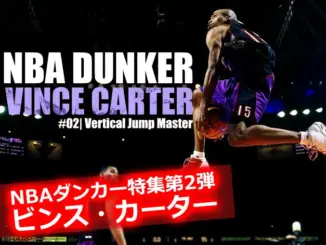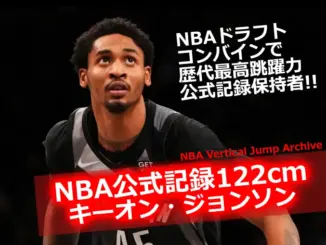NBAは2026年のオールスターゲームに向けて、これまでの形式を刷新する方針を明らかにしました。新たに採用されるのは「米国2チーム vs 世界選抜1チーム」という構成。これは単なるエンタメ形式の変更ではなく、NBAが抱える構造的課題——国際選手の評価、競技力の均衡、グローバル展開——に対する戦略的な回答でもあります。
本記事では、この新形式の背景と意図、ユーロバスケット2025でのフィンランド代表の快進撃、そして往年ファンの声や選手負担の現実を通じて、NBAオールスターの「現在地」と「未来像」を構造的に読み解きます。
NBAオールスター2026 開催情報(現時点)

- 開催日程:2026年2月13日(金)〜2月15日(日)
- 2月13日(金):ライジングスターズ
- 2月14日(土):スキルチャレンジ/3ポイントコンテスト/スラムダンクコンテスト
- 2月15日(日):第75回NBAオールスターゲーム本戦
- 開催地:カリフォルニア州イングルウッド(ロサンゼルス郊外)
- 会場:インテュイット・ドーム(ロサンゼルス・クリッパーズの新本拠地)
- 開催回数:ロサンゼルスでの開催は通算7回目(過去最多)
- 特記事項
- インテュイット・ドームは2024年8月完成予定の最新アリーナ
- クリッパーズ単独のホームアリーナとしては初のオールスター開催
- NBAコミッショナーのアダム・シルバーは「革新的なバスケットボール体験を約束する」とコメント
新形式の概要:米国2チーム vs 世界選抜
- 従来の「チームUSA vs チームワールド」や「ドラフト形式(レブロン vs KD)」からの脱却
- 米国出身選手を2チームに分け、世界選抜と対戦
- 世界選抜にはヨキッチ(セルビア)、ドンチッチ(スロベニア)、マルカネン(フィンランド)などが候補
- NBAは「競技力の均衡」と「国際市場の拡大」を狙っていると見られる
この形式は、米国選手の内部競争を促しつつ、国際選手の評価を再構築する試みとも言えます。
出典:NBA公式発表(2025年9月13日)、NBC Sports報道、Bleacher Report分析記事
フィンランド代表の快進撃:国際評価の再構築
ユーロバスケット2025では、ラウリ・マルカネン率いるフィンランド代表がジョージア、セルビアを破り、史上初の準決勝進出を果たしました。これは単なる番狂わせではなく、国際選手の競技力とリーダーシップが再評価される契機となっています。
- マルカネンはNBAでも平均20得点以上を記録する実力者
- フィンランド代表ではエースとして戦術の中心に
- 世界選抜チームにおける「欧州系スターの役割」が再定義されつつある
出典:FIBA公式サイト、ESPNユーロバスケット特集、BasketNewsインタビュー
欧州系スターの役割再定義が形式変更に与える影響

かつてのオールスターでは、ヨーロッパ出身選手は「話題性」や「国際色の演出」として選抜されることが多く、実際の試合ではプレータイムや役割が限定的でした。しかし近年では、ヨキッチ(セルビア)、ドンチッチ(スロベニア)、マルカネン(フィンランド)といった選手が、NBAのMVPレースやチームの中心選手として活躍するようになり、単なる“国際枠”ではなく“競技力の柱”として認識されるようになっています。
この変化が、オールスター形式に以下のような影響を与えています:
- 世界選抜チームの競技力が「演出」から「本気の対抗勢力」へと進化
→ 米国2チームに分けることで、世界選抜が対等に戦える構成に - 欧州スターが“補完役”から“中心軸”へ
→ ヨキッチが司令塔、ドンチッチがスコアラー、マルカネンがストレッチ4として機能する構成が可能に - 国籍ではなく“プレースタイル”でチーム構成を考える流れ
→ 世界選抜は「パス重視・IQ型」の欧州スタイルで、米国チームは「アスレチック・個人技型」となる可能性 - ファンの視点も変化
→ 「世界選抜が勝てるかもしれない」という期待が、形式そのものの魅力を高めている
このように、欧州系スターの台頭は、形式変更の“理由”であると同時に、“成立条件”でもあるのです。彼らが中心となって機能することで、世界選抜という形式が「見せ物」ではなく「競技イベント」として成立する土台が整ってきたと言えるでしょう。
オールスター形式の変遷:伝統と実験の交錯
| 年代 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|
| 1951〜2017 | EAST vs WEST | 伝統的なカンファレンス対決。地域性とチームアイデンティティが明確 |
| 2018〜2023 | ドラフト形式 | レブロン、カリー、KDなどがキャプテンとなり選抜チームを編成 |
| 2024 | EAST vs WESTに一時回帰 | 7年ぶりの復活も、競争力に欠けるとの批判もあり |
| 2025 | 4チームトーナメント形式 | シャック、バークリーらがGMとしてドラフト。実験的な構成 |
| 2026(予定) | 米国2チーム vs 世界選抜 | 国際化と競技力均衡を狙った新構成。NBCの提案が背景に |
出典:NBA公式アーカイブ、The Athletic特集記事、Sports Illustrated年表
往年ファンの声:「やっぱりEAST vs WESTが好きだった」
形式変更には、ファンからさまざまな反応が寄せられています。特に往年のNBAファンの間では、「選手の国籍に関係なく、イースト vs ウエストで戦う伝統的な形式が一番しっくりくる」という声が根強くあります。
- 「昔のように、所属カンファレンスのジャージーを着て戦う姿が見たい」
- 「国籍で分けるより、チームのアイデンティティで分けた方が感情移入できる」
- 「レブロン選抜 vs カリー選抜のドラフト形式も面白かったけど、やっぱりEAST vs WESTが王道」
- 「形式を変えても、選手が本気を出さなければ意味がない」
- 「ヨキッチやルカはオールスターで手を抜くから、世界選抜形式は盛り上がらないかも」
コメント抽出元:Reddit(r/NBA)、X(旧Twitter)上のファン投稿、YouTubeのNBA公式動画コメント欄(2025年9月13日時点)
選手負担という現実的な壁
形式変更が進む一方で、選手の負担は年々増加しています。
- レギュラーシーズンの過密日程
- 国際試合や代表活動との両立
- メディア対応・スポンサーイベントの増加
- 怪我リスクとキャリアへの影響
これらを踏まえると、オールスターに「競技力」と「エンタメ性」の両方を求めるのは、構造的に無理があるという見方もできます。
出典:NBA Players Association(NBPA)声明、ESPN Injury Tracker、The Ringer分析記事
MASAKARI的視点:ここ数シーズンのAS形式の変容は構造改革か迷走か?
「EAST vs WEST」というオールスターの形式から脱した最近のNBAオールスターは、まだ「完成形」には至っていないと考えられます。ここ数シーズンのリーグの試行錯誤は構造改革ととらえていいのか迷走ととらえていいのか、難しいところですね。
この試行錯誤の期間がどれほど続くかは分かりませんが、個人的には東西対決(EAST vs WEST)がシンプルでいいのではと思います。前半は緩い感じですが、点差の無い第4クォーター終盤の本気のプレイは興奮ものでした。
今後のオールスターの形式を予想してみた。
- EAST vs WEST形式の復活+世界選抜との別枠対戦
- 選手投票+AI分析によるハイブリッド選抜
- 負担軽減のためのミニゲーム形式(3on3、スキルズチャレンジ拡張)
- ファン参加型のリアルタイム投票による試合展開の変化
どこに落ち着くかは分かりませんが、ファンの声と選手の現実をどう折り合いをつけるかが、今後の鍵になるでしょう。AI分析による、選抜はありそうですね。
オールスター形式変更の報道日と出典元
- 報道日:2025年9月4日(日本時間)/現地時間:9月3日
- 報道者:シャムズ・シャラニア(ESPNシニアNBAインサイダー)
- 報道内容:2026年のNBAオールスターは、米国出身選手2チーム+世界選抜1チームによる総当たり形式が検討されている